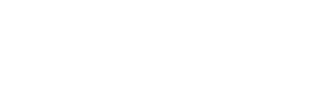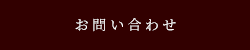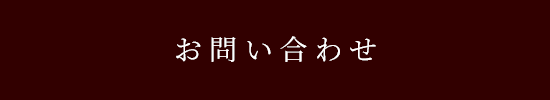気候変動は人権にも悪影響?知っておくべき「環境と人権」の関係(2025年1月 サステナブル・ブランド ジャパン(SB-J)掲載)

※2025年1月20日付のサステナブル・ブランド ジャパン(SB-J)の記事を一部変更して掲載しています。
前回(第5回)の記事では、「児童労働」という人権リスクについて説明し、企業はどう取り組むべきかを説明しました。今回は環境問題(気候変動)と人権がどのように影響し合うのか、取り上げます。
「環境」問題は「人権」問題という世界の認識
最近、これまで以上にニュースなどで「気候変動」「地球温暖化」「脱炭素」「GX(グリーントランスフォーメーション)」といった言葉を目にするようになりました。実際に、猛暑日が増えたり、集中豪雨などの激しい天候が起こったりしていて、私たちの生活にさまざまな影響を与えています。
気温や雨の降り方が長い期間(数十年単位)で変わっていくことを「気候変動」といいます。気候変動は、今や世界的に重要な問題となっていて、各国や企業が急いで対応を進めています。以前は、気候変動は「環境問題」として考えられることが多かったのですが、近年、「気候変動は人権問題でもある」という考え方が広がっています。人間には、生きる権利や安全に暮らす権利がありますが、気候変動の影響によって、それらの権利が脅かされているのです。例えば、大雨や強風、山火事のような異常気象が起きると、多くの人の生活や健康に大きな被害が出てしまいます。
世界保健機関(WHO)は、2030年から2050年のあいだに、気候変動が原因で起こる栄養不良やマラリア、下痢、熱ストレスなどによって、毎年25万人もの人々が亡くなると予測しています。特に、水や衛生などの設備が整っていない地域(主に発展途上国)は、十分な対策が取りにくく、大きな被害を受けやすいとされています。さらに、世界の温室効果ガス(CO2など)の半分以上は、世界人口の1割ほどの豊かな層が排出しているといわれています。一方で、排出量が少ない貧困層の人々が、食料不足や健康被害などの深刻な影響を受けているため、こうした不平等は「人権問題」として国際的に取り上げられています。
こうした背景があり、2022年に行われた国連総会では、「クリーンで健康、かつ持続可能な環境へアクセスできることは、すべての人にとっての基本的な人権である」という宣言が初めて採択されました。また、毎年開かれる気候変動に関する世界最大の国際会議であるCOPでも、気候変動が人権にどのように影響するかが話し合われています。2022年にエジプトで開かれた「COP27」では、「損失と損害(ロス&ダメージ)」というテーマが大きく取り上げられました。これは、気候変動が原因で避けられない被害を受けた国や地域に対して、支援や補償を行うしくみのことです。特に、貧しい国や小さな島国などが「自分たちの国では防ぎきれない被害に対応するため、国際社会からのサポートがほしい」と強く求めています。その後のCOP28やCOP29では、先進国を中心に「損失と損害」基金をつくり、特に脆弱(ぜいじゃく)な発展途上国を支援していく方針が決まりました。
企業が考えるべき「環境立てれば人権立たず」
気候変動によって生まれるリスクは多岐にわたりますが、気候変動への対策ばかりに注目しすぎて、人権がないがしろにされてしまうことも懸念されています。その代表例が電気自動車(EV)です。
世界中でEVが普及しているのは、地球温暖化などの気候変動を抑える対策として期待されているからです。しかし、EVのバッテリーをつくる際に使われる鉱物であるコバルトには、人権問題が関わっているのです。コバルトの埋蔵量の約半分はアフリカのコンゴ民主共和国にあります。ここでは、手作業でコバルトを採掘している鉱山があり、その多くが無認可の「違法」な鉱山です。こうした鉱山では、落盤(鉱山が崩れること)や窒息で亡くなる事故が頻繁に起こります。また、コバルトの粉じんを吸って呼吸器の病気になる人も多く、11~15万人ほどいる採掘労働者のなかには多くの子どもも含まれています。こうした児童労働は深刻な問題です。
国際NGOであるアムネスティ・インターナショナルは、2017年にこの問題を指摘する報告書を発表しました。そこでは、コンゴ産のコバルトを使っている可能性がある企業29社の名前が挙げられ、その中にはダイムラーやGM、テスラなどの電気自動車メーカー、ソニーなどのバッテリーメーカーも含まれていました。ソニーはこの報告を受けて、2018年9月に初めてESG(環境・社会・企業統治)に関する説明会を開き、「児童労働などの人権侵害への取り組みを強化する」という方針を公表しました。
また、再生可能エネルギー(風力や太陽光など)を利用した技術にも、銅やコバルト、ニッケル、リチウムなどの金属が必要です。こうした金属の採掘現場では、EVのコバルトと同様に、強制労働や児童労働など、人権問題が起こるリスクがあります。さらに、採掘による周辺地域の環境汚染が進むことで、住民の健康に悪影響が出ることも心配されています。
気候変動は、国境や世代を超えて、私たち全員が直面している大きな課題です。地球温暖化を食い止めるための対策や、すでに進んでしまった気候変動に伴う異常気象などへの備えは重要です。しかし、その対策を進めるあまり、人権問題を見落としてしまっては意味がありません。いわゆる「環境立てれば人権立たず」の状況を避けるため、企業が環境デューディリジェンス(環境に関する調査)を行うとき、人権の視点も同時に取り入れることが求められています。
環境と人権の両立を目指して
国連が示す「ビジネスと人権」の指導原則では、自社が直接起こす人権問題だけではなく、サプライチェーンの中で起こりうる問題についても、企業が対策すべきだと示されています。気候変動対策として使われる製品の材料や製造過程にも、人権問題のリスクが存在するかもしれないのです。
そのため、「環境」と「人権」はどちらか一方だけを重視すればいいというものではなく、それぞれがどのようにつながっているかを考えながら、両方を大切にしていく視点が必要です。企業をはじめ、私たち社会が、このつながりを理解して行動していくことの重要性が高まっています。
第7回となる次回は、「AIと人権リスク」の関係性について解説します。
株式会社オウルズコンサルティンググループ
プリンシパル
大久保 明日奈
関連レポート・コラム
「児童労働ゼロ」の実現を目指して(2024年12月 サステナブル・ブランド ジャパン(SB-J)掲載)
【連載】繊維・ファッション業界の指針となるSDGs -グローバル企業の調達ガイドラインの変化-(2020年3月執筆記事)
「ビジネスと人権」とは|指導原則のポイントと国際的な動向
「人権DD」とは|基本的なプロセスとポイント
「地政学リスク」とは|事業環境の変化に備える
関連サービス