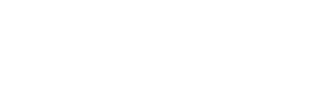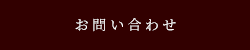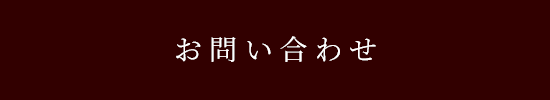近年、企業に「ビジネスにおける人権尊重」への取り組みを求める動きが加速している。2011年に国連で採択された「ビジネスと人権に関する指導原則」(以下、国連指導原則)はあらゆる企業に「人権を尊重する責任」があることを初めて明言し、その後欧米を中心として企業に人権への対応を義務付ける法律が次々と制定されている。日本でも政府が2022年9月に「責任あるサプライチェーンにおける人権尊重のためのガイドライン」を策定し、企業の人権への取り組みを後押しした。
企業に求められる人権対応として、国連指導原則で「人権方針の策定」「人権デュー・ディリジェンス(事業を通じて及ぼしうる人権への悪影響を特定し、防止・軽減するための取り組み)の実施」と共に求められているのが、人権侵害が起きてしまった時にそれを見つけ出し、対応するための仕組み「グリーバンス(苦情処理)メカニズム」の整備だ。本稿ではグリーバンスメカニズムとは何か、企業が留意すべき点は何かを中心に解説する。
国連「ビジネスと人権」作業部会も注目する日本企業の「グリーバンスメカニズム」
「日本には人権に関する構造的な課題がある」これは2024年6月に国連人権理事会の「ビジネスと人権」作業部会が行った記者会見でのコメントだ。2023年に旧ジャニーズ事務所での性加害の問題を取り上げたことで一気に注目を集めたこの作業部会は、各国の人権に関する政府・企業の課題や取り組みを調査し、勧告を行っている。日本については昨年夏に初めて調査を実施し、その結果を踏まえ報告書を公表した。冒頭のコメントはその際に出されたものである。
作業部会は旧ジャニーズ事務所の問題に限らず、賃金・管理職登用における男女間の格差、アニメーション業界の長時間労働等日本の人権を巡る様々な問題を指摘しているが、その中で企業の「グリーバンスメカニズム」が取り上げられているのをご存知だろうか。報告書には「日本のビジネスセクターに向けた勧告」という章があり、実はその冒頭に挙げられているのが「国連指導原則に基づくグリーバンスメカニズムの設立」なのだ。報告書では、上場企業の中でも人権侵害の被害者への対応を具体的に定めている企業が半数程度しかないことや、仮に通報窓口があっても被害者が報復を恐れて通報できないケースがあること等が指摘されている。すなわち、人権侵害の被害者の声を拾う「受け皿」を用意するのは当然のこと、それがしっかり機能し、実効的な救済が提供されるような一連の仕組みを日本企業がいかに整備していくのか、というところに国際社会からの注目が集まっていると言えるのだ。
「内部通報窓口を置いていれば十分」ではない
「グリーバンスメカニズム」と聞いて「わが社には内部通報窓口があるから必要な対応は既にできている」と思った人もいるのではないか。しかし「内部通報窓口」と国連指導原則等の国際規範が求める「グリーバンスメカニズム」は異なっている点に注意が必要だ。
第一に、グリーバンスメカニズムを利用できる主体の範囲は内部通報窓口よりも広い。A社の内部通報窓口に通報可能なのは基本的に「A社で働いている人」だ。一方、グリーバンスメカニズムではA社の事業活動によって影響を受けるあらゆるステークホルダーが利用対象となる。例えばA社が工場を設置する地域の周辺に住む住民や、A社の製品・サービスを利用する消費者、A社から部材の発注を受けているサプライヤーの従業員等も通報可能だ。
第二に、グリーバンスメカニズムで取り扱う通報の内容も内部通報窓口とは異なる。内部通報窓口では「国民の生命や身体、財産等の保護に関する法令に違反する行為」を扱う。その中には人権に関わるものも含まれているが、グリーバンスメカニズムで想定する「人権侵害」の範囲はより広い。仮に法令に違反していなくても、例えば広告での表現が差別的ではないかとしてSNS等を通じて炎上するケース等、一般消費者やメディアから人権の観点で批判を浴びるような場合も対象になり得る。
すなわち人権に関するグリーバンスメカニズムについては「内部通報窓口を置いていれば十分」と言うことはできないのだ。
「形だけ」のメカニズムにならないために~国連指導原則が求める要件とは
では従業員以外にも誰でも通報ができ、法令違反以外も含む人権の問題を扱える窓口を設置すればそれで十分か、というとそうではない。国連指導原則ではグリーバンスメカニズムに求められる8つの要件を示しており、メカニズムが「形だけ」に終わらず機能するためにはこれらを満たすことが必要になる(図表)。
日本企業の多くが満たしていないと考えられるのが「アクセス可能性」だ。例えば日本語を話せない海外子会社・海外取引先の従業員がいるにもかかわらず、窓口の対応言語が日本語のみというようなケースがこれにあたる。ビジネス上のやり取りで使用される日本語以外の言語を含め、複数言語での対応の必要性がないか、今一度検討してみてほしい。また「通報した結果降格処分を受ける」といった報復の恐れがあればそれもアクセスの障壁になる。事前に報復を防止する措置のほか、報復が発生した場合に事後的に対応できる仕組みを整備することが必要だ。例えば米自動車大手のGeneral Motorsは、匿名での通報を可能とすることで、通報者が特定されて不利益な取り扱いを受けることを防ぐだけでなく、案件終了後に利用者へのアンケートを実施して報復が行われていないかを確認したり、万一報復があった場合に通報できる窓口を周知したりしている。
「予測可能性」について、通報を受け付けた後の処理手続きを社内で何かしら文書化している日本企業は少なくないだろう。しかし国連指導原則等の考え方では、あらゆるステークホルダーがメカニズムを利用する可能性がある以上、こうした手続を社外に向けてもできるだけオープンにし、予測可能性を高めることが求められている。近年では自社のメカニズムについて「何を通報できるか」「通報した後に何が起きるか」等の情報を「手続規則」という形でまとめ、ウェブサイト上で公表している例も見られる。例えばシンガポールの小売大手のWilmarは「Grievance procedure」を作成・公表しており、通報を受け付けてから事実関係の調査・対応に至るまでの流れや、各段階にどの程度の期間を要するかの目安等を示している。このように手続きを透明化することは不要な誤解や利用者との間での行き違いを避けることにも資するだろう。
「自社で全て対応」でなくてもOK。外部イニシアチブへの参加も選択肢
国連指導原則等の国際規範に対応したグリーバンスメカニズムを自社で全て整備することは簡単ではない、と思った人もいるかもしれない。こうした場合、自社での設置に加え、外部団体が設立するグリーバンスメカニズムへの参加も一つの選択肢になり得る。国連の指導原則では「企業としては必要に応じ外部(政府、企業、NGO等)が提供する苦情処理メカニズムに参加することも認められる」としているほか、日本政府のガイドラインでも「企業は、企業とそのステークホルダーに関わる苦情や紛争に取り組む一連の仕組みである苦情処理メカニズムを確立するか、又は、業界団体等が設置する苦情処理メカニズムに参加することを通じて、人権尊重責任の重要な要素である救済を可能にするべき」としている。
日本では一般社団法人ビジネスと人権対話救済機構(JaCER)が提供する「対話救済プラットフォーム」が外部団体の設立するメカニズムの一例として挙げられる。同プラットフォームは国連の指導原則を踏まえて設計・運営されており、加盟した企業についての通報を受け付け、弁護士等の専門家が必要に応じて通報処理に助言を提供することが可能だ。既に様々な業界の大企業が利用している。自社に既にある窓口の状況や事業活動により影響を受けるステークホルダーの種類等を考慮しつつ、こうした外部イニシアチブを必要に応じて活用していくことが望ましい。
グリーバンスメカニズムは企業の人権対応改善の「機会」
グリーバンスメカニズムの整備は、企業の人権対応の中で最後に挙げられることも多いが、けして他の取り組みよりも遅れて対応して良いものではない。例えば人権デュー・ディリジェンスを実施する中で「自社の事業活動によってどのような人権への負の影響が生じているか」を分析する際にグリーバンスメカニズムで得られた情報を活用する等、他の取り組みと並行して取り組んでいくことが必要だ。
日本企業の中では通報が上がってくることを「問題」と捉える向きもあるかもしれない。しかし人権侵害やその疑いがあるにもかかわらずそれを放置し、事が重大化してから発覚する方がよほど大きな問題だ。人権への悪影響を早期に検知し、必要な手を打つことで、同じような事態の再発を防ぐことにも繋がる。すなわちグリーバンスメカニズムは企業の人権対応を改善する「機会」になるとも言えるのだ。
株式会社オウルズコンサルティンググループ
マネジャー
石井 麻梨
関連レポート・コラム
「ビジネスと人権」をめぐる国内外の最新ルール動向(2024年9月 サステナブル・ブランド ジャパン(SB-J)掲載)
「第12回 国連ビジネスと人権フォーラム」の速報レポート(2023年12月 JBpress掲載)
【第11回国連ビジネスと人権フォーラム 速報レポート】ライツホルダーと共に歩むべき「ビジネスと人権」の次の10年 (2022年11月 JBpress掲載)
「ビジネスと人権」とは|指導原則のポイントと国際的な動向
「人権リスク」とは|グローバル企業の事例から見る課題
「人権DD」とは|基本的なプロセスとポイント