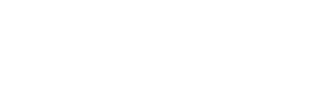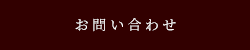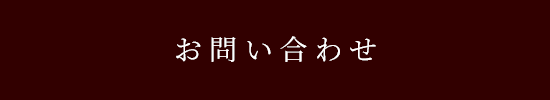「2025年の始まりにあたり、企業が押さえておきたい『ビジネスと人権 5つの主要トレンド』」(2025年1月 JBpress掲載)

※2025年1月10日付のJBpressの記事を一部変更して掲載しています。
最近、経済ニュースなどで「人権」という単語を目にする機会が増えたと感じている方は多いだろう。数年前までビジネスの世界でほとんど目にすることのなかった「人権」という言葉が、近年経営の重要アジェンダとして注目されている。世界規模でビジネスを展開する大企業が増え、社会の中で企業の影響力が増すにつれ、企業が人権に悪影響を及ぼすことも増えてきた。こうした中、国や政府だけでなく企業も事業活動の中で人権を守り尊重していくべきだという考え方(「ビジネスと人権」と呼ばれる)や、そのための取り組みが国際的にもルール化され、ますます重視されるようになってきた。
本レポートでは2025年の始まりにあたり、企業が把握しておきたい「ビジネスと人権」の5つの主要なトレンドを取り上げて解説する。
1.「ものづくり」以外の世界でも顕在化する人権リスク
ここ数年、特にサービス業関連の企業の経営陣などに「ビジネスと人権」について話すと「わが社は製造業のように原材料を調達していないので、児童労働や強制労働のような深刻な人権リスクは特にない」という反応が返ってくることが少なくない。確かにこれまで注目を集めてきた人権リスクの中には、新疆ウイグル自治区における強制労働やアフリカのコバルト採掘場での児童労働など、いわゆる「ものづくり」の世界を中心に見られるものが多かった。
しかし、人権リスクはけして製造業だけの問題ではない。自社内でのハラスメントや長時間労働などのリスクは業種を問わず注意を要するほか、サービス業・IT業など「非・製造業」にあたる分野でも、業務委託先などで人権リスクが顕在化する恐れはある。典型的な例の一つが、2023年にChat GPTの開発過程で発覚した人権侵害だ。Chat GPTを開発する米国のAI研究機関Open AIは、米国のSama社に、有害コンテンツを識別するためのラベリング作業を委託していた。Sama社は米国に拠点を置きつつアジアやアフリカで多くの労働者を雇用している企業だが、ケニアの労働者が時給2ドルで児童虐待、性的虐待、殺人、自殺、拷問といった過酷な内容が含まれるコンテンツの確認・ラベル付けの作業を長時間にわたり行わされていたことが明るみに出たのだ。従業員の中で「この仕事を通じて精神的な傷を負った」「拷問だった」とメディアに訴える人が複数現れ、OpenAIは各所からの批判にさらされた。「海外の話であって、日本には関係ないだろう」と思ってはいけない。この後触れるように、日本でもメディア業界などで深刻度の高い人権侵害の事案が見られており、「ものづくり」に関わらない企業にとっても人権リスクは決して「他人事ではない」ことを改めて認識すべきだ。
2. 「ビジネスと人権」で周回遅れのメディア・エンターテイメント業界の動きに注目
近年、日本ではメディア・エンターテイメント業界での人権意識の低さが浮き彫りになった。元タレントが告発しBBCが報道したことで大きな話題を呼んだ大手芸能事務所での性加害問題は象徴的な一例だろう。作業部会の会見では「日本のメディア企業は数十年にもわたり、この不祥事のもみ消しに加担した」とのコメントもあり、芸能事務所だけでなくそれを取り巻くメディア業界の責任にも光が当てられることとなった。さらに2024年に公表された作業部会の「訪日調査報告書」では、メディア・エンターテイメント業界全般について、女性ジャーナリストや俳優に対するセクハラ、アニメーターの低賃金や長時間労働などの問題を指摘しており、国際的にも厳しい目が向けられている。
「コンテンツ内での差別的な表現」にも注意が必要だ。2024年に人気バンドMrs. GREEN APPLE(ミセス・グリーン・アップル)のMVに「歴史や文化的な背景への理解に欠ける表現が含まれていた」として、動画の公開が停止されたことは記憶に新しい。公開停止となったMVは、コロンブスに扮したメンバーの一行が南の島を“発見”するなど、植民地主義や奴隷制を想起させるような内容であったため、「植民地主義を肯定している」「人種差別をエンタメ化している」といった批判の声が国内外から次々に上がった。本件に限らず、日本のコンテンツが国際的な人権感覚からすると「ずれている」と捉えられるケースは少なくない。
既に国内の主要テレビ局で新たに人権方針を策定するなどの動きが出てきているが、今後こうした取り組みが一時的なものに終わらず継続的なものとなっていくかがますます注目される。
3. オンラインビジネスでますます留意すべき「子ども」の人権
人権対応を進める上で欠かせない視点の一つが、「誰の」人権が侵害されるかだ。特に権利を持つ主体(ビジネスと人権の世界では「ライツホルダー」と呼称する)が弱い立場にあるほど、被害を受けた時に声を上げたり行動したりすることが難しく、深刻な影響が及ぶことが想定される。ここでは近年のルール・社会動向も踏まえ「子ども」の人権に注目したい。
従来から、玩具・アパレルメーカーなど子どもを対象にしてきた企業では、安全面などで「子ども」の人権を意識する機会もあっただろう。一方、近年では例えば写真・動画投稿やチャット機能を持つSNSアプリなどのオンラインサービスを子どもが利用する機会が増えており、その中で懸念される人権リスクもある。
一例は子どものプライバシー保護だ。海外では先行してルール作りが進んでいる。米国では2024年に、17歳未満の子ども向けにオンラインサービスを提供する企業に対して、製品等を設計する際に子どもの被害を防止・軽減するための「合理的な措置」を講じることを義務付ける法律(Kids Online Safety Act)や、17歳未満の子どもから同意なしに個人情報を収集することを禁止する法律(Kids Online Privacy Act)が次々と整備された。日本政府も、2024年にスマートフォンアプリを手掛ける事業者向けの指針を改訂して、子ども向けにやさしく書かれた個人情報規約の作成を求める方針を示している。子どものプライバシー侵害は、最悪のケースでは児童買春や児童ポルノ等の悪質な犯罪に繋がるケースもある。各国政府もこうした深刻度の高さを認識して対応を急いでいる形だ。
例えばSNSを通じてこれまでになかったつながりやアウトプットの機会を得るなど、従来なかったオンラインサービスで子どもが受ける恩恵が大きいのも事実だ。一方、今後企業は個人情報漏洩に限らず、誹謗中傷や依存など、子どもがサービスを利用する際に起こり得る様々な人権リスクを想定し、例えば保護者の事前同意や確認、NGワードの検知などの仕組みを通じてそれらを防止・是正していくことが求められる。
4. 製品・サービスの「販売先」での人権リスクにも留意せよ
近年、大企業を中心として、自社内での人権リスクに対応するだけでなく、原材料等を調達しているサプライヤーや業務委託先、言い換えればサプライチェーンの「川上」にあたる取引先に対しても人権尊重を求める動きが活発化している。取引先企業に対し、人権の尊重を含めたサプライヤーへの要求事項をまとめ、「調達ガイドライン」等の形でルール化している企業も少なくない。
一方、これまであまり注目されてこなかったのが「売った後」のリスクだ。BtoC企業の場合は消費者からの意見や訴訟に直面することもあり、自社製品・サービスが販売された後に人々の安全や健康等に悪影響を及ぼしていないかを意識する局面が多少なりとも存在するが、BtoB企業の場合はこうしたケースは少なく、「川下」の人権リスクに関する意識は特に希薄であったと言わざるを得ない。しかしいまや企業や政府を顧客とするビジネスであっても、販売先で起きることについて「売った後のことは知りません」では済まされない時代になっている。
例えば2022年2月に始まったロシアによるウクライナへの軍事侵攻では、ロシア軍のドローンに複数の日本企業のカメラやエンジンが活用されている可能性があると報じられた。2024年に採択されたEUのCSDDD(企業に対し、事業活動による人権や環境への悪影響を予防・是正することを義務付ける「企業持続可能性デュー・ディリジェンス指令」)においても「川上」だけでなく「川下」も含む「バリューチェーン全体」を通じた対応が必要であることが改めて確認された。企業は自社の製品・サービスが「販売先を通じて間接的に人権侵害に加担している」可能性も視野に入れた上で、人権対応を進めていく必要があるだろう。
5. もはや自社内だけの問題ではない「ハラスメント」
ハラスメントは従来、基本的に社内で起きる問題と考えられてきた。しかし近年、社外の関係者との間で発生するハラスメントにも注目が集まっている。
一つはカスタマーハラスメント(カスハラ)だ。「お客様は神様なのだから、何をされても我慢すべし」という考え方には以前から疑問が呈され始めていたが、近年、国の調査等でも悪質なクレーマーの実態が明らかになり、社会的な問題と捉えられるようになった。2022年には政府が「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」を公表し、企業がカスハラについて具体的にとるべき対策などを示した。2024年には東京都が自治体として初めて「東京都カスタマーハラスメント防止条例」を策定し、カスハラの禁止を明記するとともに、事業者にも適切な措置を講じるよう努力義務を課している。今後はカスハラに関する法改正も予定されており、企業側もそれを見据えて対応することが求められるだろう。
もう一つ注目すべきはリクルートハラスメント(リクハラ)だ。国内ではこれまでにも大手企業の従業員がOB訪問の際に女子学生にわいせつ行為を行い逮捕される等の事案が複数発生していたが、2024年には政府が企業に対して、就活生についてもハラスメント防止に向けた対応を義務付ける方針を示した。「憧れの企業に入りたい」という求職者の想いを利用した不当な行為に、国も社会もきわめて厳しい姿勢をとり始めている。
企業は、顧客や求職者など社外関係者との間で起きるハラスメントも念頭に置き、これまで実施してきた「ハラスメント対策」の在り方を今一度見直すことを迫られている。
以上、2025年の始まりにあたって、「ビジネスと人権」に関する5つの主要なトレンドを解説した。人権尊重に取り組もうとする企業は、企業に人権を尊重する責任があることを初めて明記した2011年の国連「ビジネスと人権に関する指導原則」等に沿って取り組みを進めていくことが基本となる。一方、国内外で新たに策定されるルールの動向や社会情勢の変化、これまでにない技術・サービスの登場等を受けて、考慮すべき人権リスクの範囲や、取り組みにあたって注意すべき観点が刻々と変化していく点には注意が必要だ。本レポートで取り上げたものも含め、企業には「ビジネスと人権」を取り巻くトレンドの変化に常にアンテナを張り続けることが求められる。
株式会社オウルズコンサルティンググループ
マネジャー
石井 麻梨
関連レポート・コラム
今、すべての企業が注目すべき「ビジネスと人権」とは?(2024年8月 サステナブル・ブランド ジャパン(SB-J)掲載)
「ビジネスと人権」をめぐる国内外の最新ルール動向(2024年9月 サステナブル・ブランド ジャパン(SB-J)掲載)
「ビジネスと人権」とは|指導原則のポイントと国際的な動向
「人権リスク」とは|グローバル企業の事例から見る課題