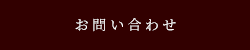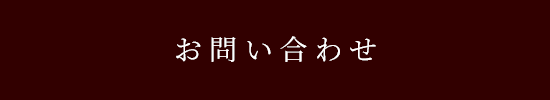※2024年6月17日付の民放onlineの記事を掲載しています。
「ビジネスと人権」とは―なぜ、今すぐに取り組むべきなのか
最近、「ビジネスと人権」や「人権デュー・ディリジェンス」といった言葉をニュース等でよく目にするようになったと感じるビジネスパーソンは多いことだろう。数年前までは倫理や道徳を説く文脈でしか語られてこなかった「人権」という単語が、今や企業経営の根幹に関わる重要アジェンダとして国内外で大きな注目を集めている。
近年、中国・新疆ウイグル自治区における強制労働の疑いや、ロシアによるウクライナへの軍事侵攻など、国際社会における人権問題が続々と顕在化していることに加え、国内では特にメディア/エンターテインメント業界においてさまざまな人権リスクが顕在化している。特に昨年(2023年)、国内大手芸能事務所における性加害問題が大きく報じられ、取引先企業も含めて対応を問われる事態となったことは記憶に新しい。この問題はいまだ解決したと言えない状況にあるが、こうした報道を通じて、「ビジネスにおける人権尊重」の重要性をあらためて認識した日本企業も多いものと思われる。
企業が発出する有価証券報告書を見ても、その意識の変化は一目瞭然だ。「人権」というキーワードを記載している企業が2023年度には1,002社にのぼったが、これは2017年度(140社)の7倍超にあたる。従来、日本人および日本企業は「サステナビリティの中で『環境』問題への関心は強いが、『人権』への意識が薄い」と見られてきたが、その傾向が急速に変わりつつあるのだ。
日本政府も、昨今の国際潮流を受け、「ビジネスと人権」に関する取り組みを加速させている。2022年9月には政府として「責任あるサプライチェーンにおける人権尊重のためのガイドライン」を策定し、2023年4月にはさらに経済産業省がその補足的役割を果たす「実務参照資料」を公開し、企業に取り組みを促した。また、今後、公共調達に入札する企業には人権尊重の取り組みを求める旨も発表している。
まだ国内では法制化には至っていないものの、欧米諸国では企業に人権対応を義務付ける法律が2010年代以降次々と制定されており、日本へのプレッシャーも年々強まっている。今年3月には、岸田文雄首相が「将来的な法律の策定可能性も含めてさらなる政策対応について検討していく」と、法制化の可能性に言及している。日本企業は今後の法制化の可能性も充分に見据え、「ビジネスと人権」に係る取り組みを喫緊で強化していく必要があるのだ。
企業に求められる「人権デュー・ディリジェンス」
では、企業は具体的に何を実行すべきなのか。現在、欧米を中心にさまざまなルールやガイドラインが策定されているが、全ての基盤となっているのは2011年に国連で採択された「ビジネスと人権に関する指導原則」(国連指導原則)だ。規模や業種に関わらずあらゆる企業に「人権を尊重する責任」があること、そして「企業が自ら直接引き起こしている人権侵害だけでなく、間接的に負の影響をもたらしている(事業・製品・サービスと結びついている)人権侵害にも対応しなければならない」ことを初めて明言した国際文書である。
同原則は、全ての企業に対して、人権尊重の責任を果たすための適切な対応を求めている。具体的には、人権尊重へのコミットメントを示す「人権方針」を策定すること、自社が及ぼしうる人権への負の影響(人権リスク)を特定・防止・軽減する「人権デュー・ディリジェンス」と呼ばれるプロセスを実施すること、そして負の影響が発生した場合に是正・救済するための仕組みを整備することだ。
デュー・ディリジェンスと聞くと、M&Aの際に行われる買収前の企業調査を連想するビジネスパーソンも多いだろう。だが、企業買収の是非の判断のために「一度だけ」行うアセスメントであるM&Aのビジネス・デュー・ディリジェンスとは異なり、人権デュー・ディリジェンスは「継続的に」実施し続けていくべきものだ。
自社の事業活動が引き起こしうる「人権リスク」の全体像を把握し、その深刻度や発生可能性を評価した上で、重要な人権リスクから予防・是正に取り組み、施策の効果を継続的にモニタリングし、改善を重ねていく。このプロセスを回し続けていくことで、自社が人権侵害に関与する可能性を限りなくゼロに近づけるのが目指すべき姿と言える。
メディア業界で特に注意すべき人権リスク
予防や是正に努めるべき「人権リスク」は、ビジネスにおけるさまざまな場面に潜んでいる。具体的に、メディア/放送業界で特に注意すべき人権リスクにはどういったものがあるだろうか。
代表的なものとして、例えば「差別的な表現」に関するリスクが挙げられるだろう。制作側が意図したか否かにかかわらず、放送コンテンツの中で「マイノリティに対する差別(人種や性別、出自等に関する差別)を助長する表現になっている」と問題視された例は数多い。コンテンツが差別やバイアスを含んだ表現になっていないか、人権の観点から慎重に確認を行う仕組み・体制の確立が必要だ。
また、日常でよく使われる言い回しにも人権リスクが潜んでいることがある。例えば「〇〇難民」という言葉は「〇〇を探しているが見つからない人」という意味でカジュアルに使われる場合があるが、本来の意味での「難民」当事者や支援者からすれば、難民問題の矮小化につながり得ると感じる可能性は排除できない。実際に広告等のコピーに用いた結果、苦情や批判が寄せられて取り下げとなった例もある。こうした「実際に起こっている深刻な人権侵害を軽視したり、矮小化してしまうような表現」にも注意が必要だ。このリスクをクリエイティブの現場に帰責させ、「クリエイターの人権リテラシーを上げさせる」という施策に傾倒してはいけない。コンテンツ制作の現場が発揮すべき創造性を維持したうえで、組織としての人権配慮のガバナンス体制をどう構築するが問われているのだ。まさに経営課題と言ってよいだろう。
また、もはや言うまでもなく、「長時間労働」も重大な人権リスクの一つだ。1分1秒のスケジュール遅れが致命傷となりうるメディア/放送業界では、労働環境も当然ながら過酷になりやすい。健康を害するような長時間労働や過重労働を避けるため、(すでに取り組んでいる企業が大多数であるものと思うが)労働環境の改善に向けた取り組みも引き続き必須となる。
加えて、業務プレッシャーの強さや人間関係の濃密さに起因するハラスメント(パワハラ/セクハラ等)も、業界として顕著なリスクにあたるだろう。もちろん自社内(放送局の内部)さえクリーンであればよいわけではなく、自社が関わる制作現場の中で過酷な労働やハラスメント、性加害などに苦しむ人がいれば、それが取引先の従業員やタレントであっても自社の責任が問われうる。
また、今後特に留意すべき観点として「AIが引き起こす人権リスク」にも注意が必要だ。これからの時代、放送局が扱う知的資産の多くは、生成AIを用いて作られたコンテンツと無縁ではいられない。生成AIは、コンテンツの生成過程において、他者の知的財産であるコンテンツを学習材料として取り込む可能性が高い。このプロセスで、個人の知的財産権やプライバシーを不当に侵害してしまうリスクがある。さらに、生成AIが多様な事象について「らしさ」を模倣しようと試みる中で、差別を助長してしまうケースがあるという研究結果も存在する。
今後生成AIの活用にあたっては、国内外で倫理ガイドラインの策定が進み、各放送局でもその遵守が求められるだろう。コンテンツ制作における透明性の確保、著作権および知的財産権の尊重、差別的表現の排除などに注意しながら、生成AIがもたらす利便性とリスクのバランスを適切に取っていく必要がある。
メディア業界・放送局への期待
ここで残念ながら断言せざるを得ないこととして、国内のメディア業界は、他の業界と比べて人権対応が遅れている。製造業ではすでに多くの企業が人権デュー・ディリジェンスを実施しており、流通・小売業そして金融やITサービスなど多くの業界がこれに続いているが、放送業界ではその取り組みが十分に進んでいないのが現状だ。
そこには放送業界自身の「特別意識」が残存すると分析する専門家もいる。公共性が高く、社会課題に切り込む高邁な「ジャーナリズム」のためであれば、その過程での自らの立ち振る舞いには無頓着で許されるという誤解があった旧世代のメディア人もいたかもしれない。「昔はこんなことは人権問題とされなかったのに」と懐古しても意味がない。社会は変わり、今や法令や業界ルールも変わっているのだ。
あらゆるコンプライアンスであれCSR(企業の社会的責任)であれ、最も影響力を持つガバナンスは「お客からの要請」だ。番組制作・放送の中で、発注側たる放送局が取引先に人権配慮を求めれば、メディア業界全体が大きく改善する。放送局は、自社の人権意識を高めるだけでなく、関連するタレント事務所や制作会社に対しても人権尊重を求める必要がある。適切な契約書を作成し、その中に人権配慮の条項を盛り込み、定期的な調査や監査を実施する――他の業界ではごくあたりまえに導入されつつあるこの仕組みを日本のメディア業界も取り入れる時期が来た。
放送局が「どれだけ耳目を集めるコンテンツを提供したか」のみで評価される時代は過ぎ去った。放送局には今後、「どのような番組の作り方をしたか」という「会社としてのあり方」が問われていく。差別・ハラスメント・過重労働をしない、といった最低限の人権配慮はもちろん、「より良い放送局とは」「より良いメディア企業とは」という経営哲学を再考した上での積極的な「ビジネスと人権」対応が求められる。
2024年から米アカデミー賞は「作品賞」の選出基準に「多様性の確保」を追加した。これに呼応する形で、ウォルト・ディズニー・カンパニーは、映画や番組の制作関係者(ディレクター・プロデューサー・脚本家・出演者など)におけるジェンダーや人種の構成率を定量的に発表するようになっている。すでに世界のメディア業界の「モノサシ」は変わりつつあるのだ。
ESG投資[1]の「S(社会・人権)」に関する開示ルールも刻々と具体化されつつある。人権デュー・ディリジェンスを実施し、ステークホルダー全体で人権リスクに対処することは、投資家からの信頼にもつながり企業価値を高める施策となる。「クリエイターやアーティストの能力が存分に発揮できる番組づくり」と「人権に配慮し、誰かの生きづらさを生まない放送局」は同時に成立し得るはずだ。今日の放送局の経営者に対する期待は大きい。
[1] 財務情報に「E(環境)」「S(社会・人権)」「G(統治)」の要素を加味して投資先を評価する投資手法
株式会社オウルズコンサルティンググループ
代表取締役CEO
羽生田 慶介
関連サービス