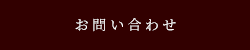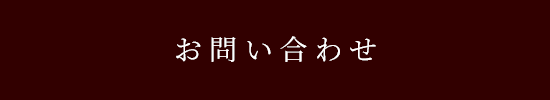※月刊アイソス2023年3月号に寄稿した内容を一部変更して掲載しています
広がり続ける国際ルール形成の「盤面」
「社会課題解決のためのルール形成」の重要性自体に異を唱える論客はいないだろう。それにも拘らずなぜ我々はこのテーマに「難局」という印象を持ち、これまでの取り組み方からの変革の必要性を感じているのだろうか。
官民のルール形成戦略に長く従事してきた筆者の考えでは、現状を「難局」たらしめている背景のひとつに、ルール形成の分野が世界的に広範囲になり続けていることが挙げられる。例えば、近年最もルール形成が具体化している「脱炭素」分野に絞って見ても、その対象となる「盤面」が広がり続けていることは明らかだ。
2022年2月にEUが策定した「欧州標準戦略(EU Strategy on Standardisation)」からもそのことが垣間見える。当該戦略で掲げられた具体的な「ワークプログラム」69項目の中で、3分の1近くを占める最大の注力テーマとされたのが家電を中心とした製品に対する「エコデザイン」だ。
これまで脱炭素については、サプライチェーンにおける温室効果ガス排出量をスコープ1・2・3と区分けして計測する方法論に関する議論がルール形成の中核を占めてきた。「GHGプロトコル」やPAS2050(カーボンフットプリント)、ISO14040(ライフサイクルアセスメント)等がその具体例だ。
そんな中でいまEUが「エコデザイン」の標準化に注力するのは、「サプライチェーンのプロセス内で実施できる脱炭素施策だけでは、もはや気候危機に対処できない」ことに気づいたからだ。
既存の製品設計を前提としている以上、どれだけ工場における再生可能エネルギー使用比率や最終財・部材のリサイクル比率を上げてみても、IPCC(気候変動に関する政府間パネル)が求める対策の水準には到底及ばないことが分かってきた。
部材がサプライチェーンに投入される前の設計段階から循環性を意識したデザインを行い、部品点数の削減や修理可能性を高めることの重要性にアジェンダがシフトしつつあるのだ。多くの企業が工場の電源構成のシフトやグリーン電力証書の検討に躍起になっている間に、欧州がさらにルール形成の盤面を広げてきた一例だ。
社会課題解決のルール形成テーマはこれから本格拡大
特に企業に直接的な影響が出やすい「情報開示」のルール形成は、これから一挙にその要求範囲が広がると考えて間違いない。G20の要請を受けて設立された「気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)」によって企業の気候関連の情報開示や金融機関の対応が変化しつつあるが、今後は「気候」だけでなくより広範な分野での情報開示が求められる。
2021年6月に設立された「自然関連財務情報開示タスクフォース(TNFD)」では「生物多様性」に関する情報開示の方向性が議論されており、2023年9月にはその最終提言がまとめられる予定だ。
また、「持続可能な開発のための世界経済人会議(WBCSD)」は2023年初の報告書の中で、人権などの社会分野をターゲットとする「社会関連財務情報開示タスクフォース(TSFD)」の設立を打ち出すとしている。
近年、例えば「脱炭素」だけをESGテーマに据えてきた企業は、この「盤面の広がり」に危機感を覚えるだろう。情報開示についても、特定の社会課題のみに限定せず、SDGs(国連持続可能な開発目標)等で示される広範な分野における企業の責任を網羅するための議論が進んでいるのだ。
例えば「気候正義(Climate Justice)」のように「気候変動対策」と「人権尊重」が関連するようなテーマもあり、それぞれの項目は相互に連関するため、必ずしも企業がとるべきアクションがこれらテーマの数に応じて乗数的に拡大するわけではない。とはいえ、大前提として、企業が理解し対応しなければならないルール形成のバウンダリーはこれから本格拡大することを認識しなければならない。
グローバルなルール競争のすべてを主戦場にはできない
このように「盤面」が広がり続けている国際ルール形成の戦線において、人的にも予算面でもリソースに限りがある日本政府や日本企業が全方位に対応することはできない。まずはこの現実を直視することが必要だ。
それぞれのルール議論は非常に重要であり、もちろん積極的に関与できるに越したことはない。だが残念ながら、今の日本にとって、今日のグローバルなルール競争に全方位的に対応する体制を整えることは現実的でない。
「ルール形成戦略」という言葉が語られるようになって年月が浅い日本では、事業戦略や産業課題に応じた適切なルール形成戦略を構築できるビジネスリーダーやコンサルタントも不足している。「標準化」領域に限定して見ても、英語が堪能で規格策定や標準化議論の豊富な経験を持つ人材は数少ない。
そして実は、そういった専門人材の所在も偏っている。産業構造審議会(2019年総会)資料によれば、ISO/IEC国際会合への中心的な参加者を年齢別で見ると、40代以下の割合が中国では6割であるのに対し日本は5%のみ。日本の場合、なんと60歳以上が43%を占めているというのだ。この事実は、新たな市場を創りながら成長するはずのスタートアップ企業の若手人材が、国際標準化の議論にほぼ参画していないことを意味する。
さらに危機感を持つべきは、かつて日本が国際標準の世界で存在感を持って活躍していた時代に前線で戦っていた専門家が、現在に至るまで同じ顔触れのままこの分野をリードしつつ高齢化を迎えていることだ。
大企業の中ですら、新たな社会構造の中心となる世代が国際標準化の議論に加わっていない可能性がある。今の日本に、拡大し続ける戦線すべてに網羅的に対応するリソースはないことが感じ取れるだろう。
他方、国際標準化において近年急速に存在感を増している中国の強みのひとつは人材の豊富さだ。ドキュメントワークに長けたエンジニア、テクノクラート(技術官僚)、英語人材が国内外に多く存在し、先端分野のルール形成に全方位的に対応できるだけのリソースがある。
結果、ISOとIECにおける委員会設置提案数は全体の4分の1にものぼり、ITUにおける通信分野の規格提案数も圧倒的となった。2020年より中国の大手発電企業の舒印彪氏がIEC会長に就いている背景のひとつにも、この潤沢な人材に支えられている事実がある。
リアリティをもって今後の官民のルール形成戦略を考えるにあたり、まずはこの日本のリソース制約に関する認識と諦観が必要だ。その上で、戦略的にとるべき方向性を打ち出したい。
ルール形成戦略提言①:「規範づくり」は欧州に委ね「問題解決」レイヤーに注力せよ
企業による社会課題解決には二つのステージがある。ひとつが「Do No-Harm(害をなさない)」という視点、すなわち「負の影響の低減」だ。大気中に炭素を「排出しない」こと(カーボンニュートラル)や、海洋にプラスチックを「流出させない」こと等の、「~~しない」と表現される分野がこれにあたる。
もうひとつが「Problem Solving(問題解決)」の視点、すなわち自社サプライチェーンを身綺麗にすることを超えた、より積極的な課題解決だ。前述の例になぞらえれば、大気中の炭素の吸収・除去などのカーボンネガティブの取り組みや、既に海中浮遊してしまっているプラスチックの回収・再活用がこれにあたる。
また、「必ずしも自社に直接的な原因が無い社会課題の解決に貢献する」こと、例えば貧困・難民問題や児童虐待の解決に向けた取り組みなどもこれに該当する。
このうち前者の、経済活動による負の影響をなくすためのアジェンダ設定においては当座、欧州に主導権を委ねるのが現実的だろう。日本とEUでは、そもそも社会課題解決型ルール形成の位置づけが根本から異なると言っても過言ではない。
EUにとってルール形成は「規範力(Normative Power)」と呼ばれる根源的な「パワー」に依拠しており、これは「軍事力」「経済力」と並列に並べられる重要な存在だ。「正しい規範」を追求する力こそが、EUが国際社会に大きな力を発揮する源と考えられているi。
それがゆえ、ルール形成に際し、求める方向性や水準が現状のビジネス実態において現実的かどうかに大きく左右されることがない。目指されるのは、あくまでもEU自身や国際社会を導くための正当性あるルール内容だ。
それに対して日本では、パブリックセクター(政府)・プライベートセクター(企業)・ソーシャルセクター(NPO/NGO)の連携による「コレクティブ・インパクト」のアプローチが根付いておらず、社会課題解決のために企業の変革を促そうとしても、行動主体が企業・ビジネスになった途端に、多くのルール形成が「経済力」の内数として語られがちだ。
すると、いかに正しい規範を追求するためのルールを提案しても、必ず「中小企業にも対応可能なのか」「その対応でサプライヤーのコストが上がった場合、誰がその負担を吸収するのか」といったビジネス視点の懸念が、課題解決に向けた「あるべき姿」の議論を覆いつくしてしまう。
そもそも、こういった「規範」づくりの多くは競争領域ではなく国際的な協調領域だ。日本は経済活動における「Do No-Harm(害をなさない)」のためのアジェンダセッティングで先鋭的な提案を目指すのではなく、その先の「Problem Solving(問題解決)」のレイヤーをこそ主戦場とすべきだろう。
例えば、日本政府が掲げる「グリーン成長戦略」の中でも多く掲げられているCCUS(Carbon Capture, Usage and Storage)技術等にはより一層、国際ルール形成に積極的に取り組むことが期待される。
また他の例として、EU Horizon 2020 Research and Innovation Programmeにて助成されているネガティブエミッション技術の実用性検討の「NEGEMプロジェクト」に、アジアからは日本の九州大学と東京海洋大学のみが参加していることにも注目だ。まだまだ日本の存在感を出し得る「Problem Solving」の分野は残されている。
ルール形成戦略提言②: ルール形成の「管制高地」を築け
次に提言するのは、前述のように盤面が広がり続けるルール形成の戦場において、見晴らしのよい高い丘、すなわち「管制高地」を獲得することだ。目的は2つ。
一つ目は、グローバルに進められている数多のルール形成に対する大局観を掴み、リソースに限りがある日本にとって「どこが本当に突入すべき戦線か」「どこならば日本が価値を出せる勝算があるか」のインテリジェンスを得ること。
もう一つは、国際社会や日本にとって適切でないルール形成が行われそうになっている分野に対し、高台から駆け下りて軌道修正させたり「No」を突き付けたりする選択肢を得ることだ。
その具体的な方策のひとつが、「コンセプト規格」や「ガイダンス規格」と言われる、概念やビジョンを整理した推奨事項の集合体としてのルール形成をリードすることである。いわば「価値観」の定義に対する提案者やオーナーシップのような位置づけだ。なぜこれが重要なのか。
目まぐるしくテクノロジーが進歩する昨今、標準化をはじめとするルール形成の場が乱立している。同種のルールが複数の国際機関で議論されたり、並行して進んでいる標準化の内容と齟齬がある議論が起きたりする可能性が高まってきたのだ。
これを調整するために国際標準であるISO、IEC、ITUでは近年SPCG(Standardization Programme Coordination Group)活動が組み込まれるようになった。また、新規の国際標準の提案時には、企画書において関連し得る「既存文書」(既存の規格等)の列挙が求められるようになっている。
このメカニズムにおいて大きな存在感を発揮できるのが、「コンセプト規格」や「ガイダンス規格」なのだ。
典型例は、組織の社会的責任を規定する有名な規格である「ISO 26000(Guidance on Social Responsibility)」だ。これ自体は認証ルールではないが、社会課題解決に関連する後続のほぼ全てのルール形成に対して整合的かを照合される対象である。継続的な影響力が極めて高い規格と言えるだろう。
このような「価値観」の定義に相当するコンセプトや概念の規格化に成功すれば、その後の他者によるルール提案に対する直接間接の「発言権」が得られるのと同等の価値となるのだ。
個別ルールとして「管制高地」の役割を果たすのが「コンセプト規格」や「ガイダンス規格」だが、ISOやIECの新たな委員会(TC)における議長や幹事のポジションを獲得することも同様の意義を持つ。
例えば、ISO TC314(Aging Societies)を英国が提案しその事務局をBSI(英国規格協会)が務めていることで、高齢者ケア施設や生活支援ロボット、福祉関連モビリティーなど、高齢化社会に関連する今後のあらゆる標準化の取り組みは、英国にも一定の照会をかけながら進めざるを得ない。
前述の通りリソースに限りがある日本には、グローバルに乱立するルール形成の動きについて広く能動的にリサーチし続けることが難しい。必要なのは、他者が仕掛ける個別のルール形成の議場のほうから、その上位概念や関連するコンセプトとの整理整合を担う立場にある日本に、適時に照会がかけられる仕組みだ。
ビジョンや調整力が求められる仕掛けであり、無論容易な方策ではない。だが、前述の社会課題の「Problem Solving」分野に焦点を絞りつつ、今後も長く機能するルール形成の「管制高地」を手に入れる戦略的価値は極めて大きいと断言できる。
ルール形成戦略提言③: 日本版「グローバル認証機関」を手に入れよ
世界各国に試験センターを保有し、広範な産業分野に対するサービスを提供できる「グローバル認証機関」が日本に存在しないことは、ルール形成の観点でも大きな問題だと筆者は以前から指摘してきた。
欧米にはスイスのSGS(Société Générale de Surveillance)やドイツのテュフ・ラインランド(TÜV Rheinland)、フランスのビューローベリタス(Bureau Veritas)など、世界各国に広がった拠点に数万人規模の試験エンジニアを抱える大企業が存在するが、日本で最大級の認証機関と言えば日本品質保証協会(JQA)など1,000人規模の一般財団法人に限られる。
ルールの規定要求事項が満たされている証明である「認証」自体はルール形成の後工程のような位置づけだが、実は認証機関はルール形成の過程においても大きな影響力を持つ。
ビジネス現場の取引条件に採用され得る実用的な認証規格の策定プロセスにおいて、認証機関には「そのルールが求める技術要件は再現可能な形で評価・認証できるか」という専門的知見の提示が求められる。すなわち、認証機関が検査・評価できないルールは成立し得ないのだ。
同時に、認証機関は「ルールの普及」においても重要な役割を果たす。先端分野で複数の規格が乱立するケースでは、「認証機関が担ぎやすい」規格のほうが普及される可能性が高いのだ。
19世紀から官民の叡智を注いで成長してきた欧州のグローバル認証機関と伍するような、フルカバレッジのサービスを提供する機関を日本で育成するというアイデアにはあまり現実味がないかもしれない。
だが、日本が重要テーマと据える分野(例えば、日本らしさを説明しやすい「衛生」や「防災」など)に絞れば、その分野に圧倒的な技術力・信頼性を持つグローバル認証機関を作りあげることはできるはずだ。
社会課題解決のためのルール形成に全セクターの叡智を
社会課題解決のためのルール形成において、必ずしも現在の国際的な議論が正しい方向に導かれるとは限らない。激動の地政学的要素により、特定の国や団体の利己的な提言が正当化されてしまう可能性も大いにある。
2023年から内閣府知的財産戦略推進事務局を中心に「国家標準戦略」が本格検討される。短期的な競争戦略の視点のみに囚われず、社会課題解決と市場創出を両立するために日本が歩むべき道筋が描かれることを期待したい。
10年後、20年後の社会や産業を持続可能な姿にするために、標準化やルール形成に携わる官民そして学術機関、ソーシャルセクターの叡智が結集すべきは今だ。
代表取締役CEO
羽生田 慶介