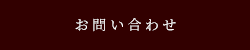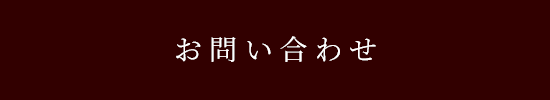※月刊アイソス2022年11月号に寄稿した内容を一部変更して掲載しています
※月刊アイソス2022年11月号に寄稿した内容を一部変更して掲載しています
国際ルール形成の大きな契機となった「国連指導原則」
2022年9月13日、日本政府は「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」を発表した。近年、企業に「ビジネスにおける人権尊重」への取り組みを求める議論が加速していることを受け、日本企業が業種横断的に活用できるガイドラインを作るべく、経済産業省が今春から検討を進めてきた内容だ。
現状、多くの日本企業が抱える「取り組みの必要性は認識しているが、具体的な方法が分からない」という悩みに応えようとするもので、経済界からも一挙に注目を集めるニュースとなった。
政府が今回のガイドラインを発出するに至った背景として、「ビジネスと人権」に関する国際ルール形成が急速に進んでいる状況がある。その最大の契機となったのは、2011年に国連で「ビジネスと人権に関する指導原則」が採択されたことだ。
この指導原則は、規模・業種・事業状況・所有形態・組織形態に関わらず、あらゆる企業に「人権を尊重する責任」が適用されることを明言した初めての国際的な文書として注目を集めた。同原則自体は法的拘束力を持たないが、その考え方は、ISO26000(社会的責任に関する手引き)やOECD多国籍企業行動指針などの国際ルールや、その後策定された各国の人権関連法に強く反映されている。
指導原則の画期的かつ特徴的な点の一つは、「企業が自ら直接引き起こしている人権侵害だけでなく、間接的に負の影響をもたらしてしまっている(事業・製品・サービスと結びついている)人権侵害にも対応しなければならない」と定めている所だ。
つまり、自社が直接的に起因もしくは意図していなかったとしても、サプライヤーへの要請が結果的に人権侵害につながってしまったり、自社の製品が販売先によって人権を侵害するような用途に使われてしまったりする可能性まで考慮する必要があることになる。

その上で、同原則は全ての企業に対して、人権尊重の責任を果たすための適切な対応をとるよう求めている。
具体的には、人権尊重へのコミットメントを示した全社的な「人権方針」を定めること、人権への悪影響を特定・防止・軽減する「人権デューディリジェンス」と呼ばれるプロセスを継続的に実施すること、そして人権への悪影響を是正するための救済や苦情処理のメカニズムを構築することだ。
この指導原則の考え方と要求事項が、後述する各国法を含む全ての関連ルールの基盤となっている。
欧米を中心に整備が進む「人権デューディリジェンス」関連法
指導原則の採択前後から、企業に人権デューディリジェンスの実施などを義務付ける法律の整備が欧米を中心に急ピッチで進んできた。
2010年に米国カリフォルニア州で「サプライチェーン透明化法」が制定されたのを皮切りに、2015年にはイギリスで「現代奴隷法」、2017年にフランスで「親会社および発注会社の注意義務に関する法律」、2018年にオーストラリアで「現代奴隷法」、2019年にオランダで「児童労働デューディリジェンス法」、2021年にドイツで「サプライチェーンデューディリジェンス法」などが次々と制定されている。
こういった人権デューディリジェンス関連法の多くは、その適用対象を国内企業のみでなく、売上高などで一定の条件を満たす外国企業まで広げている。
例えばイギリスの「現代奴隷法」は「同国で事業活動(製品/サービスの提供)または事業活動の一部を行う、(グローバルで見た連結の)年間売上高3600万ポンド以上の企業」に適用され、日本企業を含めたイギリス国内外の約1万2千社が対象となっている。
また、国によっては、違反した際の罰則や罰金が規定されていることもある。例えばドイツの「サプライチェーンデューディリジェンス法」は、サプライチェーン上の人権・環境リスクなどの管理体制の整備や定期的なリスク分析の実施を企業に義務付けており、違反時には最大80万ユーロ(平均年間売上高が4億ユーロ超の法人・団体の場合は最大で平均年間売上高の2%)の罰金が科される。加えて、公共調達への入札が最大で3年間停止されるなどの行政処分も存在する。
つまり、国境を越えて事業を展開する企業は、その本拠の所在を問わず、展開国の法整備状況に常に注意を払う必要があるのが現状だ。今や「ビジネスと人権」は、グローバル企業にとって最も重要な経営アジェンダの一つとなっている。
EU産業界を焦らせる「企業持続可能性デューディリジェンス指令案」
さらに、各国レベルでの取り組みを超え、欧州全域での導入検討が進んでいるルールもある。
それが、欧州委員会が2022年2月に発表した「企業持続可能性デューディリジェンス指令案」だ。特定の条件を満たす企業に対して、企業活動を通じた人権や環境への悪影響を予防・是正する義務を課すもので、今後この指令が発効した場合、EU加盟国はそれぞれ国内での法制化を義務付けられることとなる。
同指令の適用対象となる企業は、自社や子会社の企業活動に加え、「確立されたビジネス関係を持つ取引先」の企業活動まで含めたデューディリジェンス履行の義務を負う。違反した場合、加盟国が売上高に応じた罰金を科す仕組みだ。
適用対象は純売上高や従業員数が一定水準を超える大企業に限られるが、取引先まで含めた取り組みが求められること、また欧州企業でなくともEU域内での純売上高が大きければ対象となり得ることから、影響範囲は決して小さくないものと見込まれている。

この指令案に対して、欧州の産業界からは懸念の声も挙がっているのが現状だ。
欧州産業連盟(ビジネスヨーロッパ)は、同指令案が発表された当日に、懸念を表明する声明を出した。「企業にとって実行可能なルールになっていない」「過去数年にわたり欧州企業に課せられてきた過大な負担をさらに増やすものだ」として、企業への負担の増加を強く問題視した形だ。
欧州商工会議所(ユーロチェンバース)や欧州中小企業連合会(SMEunited)も同日に声明を発表し、中小企業が同指令案の対象から外れたことを歓迎しつつも、対象企業のサプライチェーン上に存在する中小企業への悪影響への懸念を表明した。同じタイミングで、ドイツ産業連盟(BDI)・ドイツ商工会議所連合会(DIHK)など、ドイツの主要経済団体も一斉に同指令案への懸念を示している。
他方、市民社会団体をはじめとするソーシャルセクターからは「適用対象企業を拡大すべき」といった指摘もなされており、同指令案を巡る議論は複雑化しつつある。今後、EU理事会と欧州議会での審議を経て採択に向かうこととなるが、影響を受ける可能性がある企業は議論の行方を注視しておきたい。
企業にサプライチェーンの見直しを迫る各国の輸入規制
さらに企業のサプライチェーンに直接的かつ甚大なインパクトを及ぼしているのが、各国の輸入規制ルールだ。中国の新疆ウイグル自治区における強制労働疑惑などを背景に、近年、人権侵害に加担している疑いのある製品の輸入を規制する動きが国際的に活発化しつつある。
中でも、昨今最も国際社会を騒がせたのは、米国における「ウイグル強制労働防止法(UFLPA)」の策定および施行だ。 米国の関税法307条では元々、一部または全部が児童労働を含む強制労働によって搾取・生産・製造された製品の輸入を禁止する旨が定められていた。
この条項自体は1930年の同法制定時から存在していたが、近年、新疆ウイグル自治区の強制労働疑惑を受けて、米国は同条項を活発に運用し始めた。具体的には、同条項に基づき、新疆ウイグル自治区産品等の輸入差し止め命令を発出するようになったのだ。
そこからさらに一歩踏み込む形で2021年12月に新たに制定され、2022年6月に施行されたのがウイグル強制労働防止法だ。同法により、特定の条件を満たす例外ケースを除いて、全ての新疆ウイグル自治区関連産品の輸入が原則として禁止されることとなった。
例外適用を受けるための条件には「明確かつ説得力のある証拠により、当該物品の全部または一部が強制労働によって採掘、生産、または製造されたものではないと証明すること」等が含まれ、企業による立証ハードルは非常に高いものと見込まれる。
実質的には新疆ウイグル自治区関連産品の米国への輸入がほぼ不可能になった形であり、サプライチェーンの見直しや再構築を迫られた企業も少なくない。

こうした輸入規制を強化しているのは米国だけではない。ひときわ動きが早かったのはカナダだ。カナダでは2020年7月に関税定率法が改正され、第136条の輸入禁止項目に「全体または一部が強制労働によって採掘、製造、生産された製品」が追加された。同条項は、日本を含むすべての国からの製品の輸入に適用される。
また、欧州委員会も今年9月、強制労働により生産された製品のEU域内での流通を禁止する規則案を発表した。
製品に関して強制労働を疑う充分な根拠があると判断した場合、EU加盟国の当局が調査を行い、もし強制労働が確認された場合には当該製品の回収や処分を求める旨を定めている。
同規則案は対象地域を限定していないが、米国と同様、新疆ウイグル自治区などを念頭に置いているものと見られる。今後の成立には加盟国と欧州議会の承認が必要となるが、承認を得て施行されれば2年後から適用される見込みだ。
今後、人権尊重を理由とした輸入規制強化の潮流はより一層加速する可能性もある。サプライチェーン上で輸出入を行う企業は、各国の人権デューディリジェンス法に加え、輸入規制関連法の動向についても情報収集を続けていく必要があるだろう。
日本における法制化の可能性と企業に求められる対応
ここまで見てきたように、「ビジネスと人権」に関して企業が注視しておくべきルールの数は近年加速度的に増えつつあり、その対象地域・適用範囲も拡大の一途を辿っている。
この潮流は、グローバル企業は勿論のこと、国内のみで事業を行う企業にとっても決して他人事ではない。欧米諸国の前例に倣う形で、日本でも人権デューディリジェンス等を企業に義務付ける法整備の検討が数年以内に進む可能性は高い。
本稿の冒頭で触れた「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」の策定を発表した今年2月の記者会見では、経済産業大臣が「将来的な法律の策定可能性も含めて、関係府省庁とともに更なる政策対応について検討」していくと発言している。
市民団体等からの「日本版『現代奴隷法』を整備すべきだ」といった声にはこれまで慎重なスタンスを示してきた日本政府だが、海外政府や国際投資家からの期待も高まる中、法制化の議論自体を避けることはもはや困難になる見込みだ。
日本企業は、自社が関連しうる国際ルールの動向に注意を払いつつ、国内法を含めたルールの新設や改定に伴って急な対応を迫られることがないよう、ビジネスにおける人権尊重への取り組みを適切に進めておく必要があるだろう。
株式会社オウルズコンサルティンググループ
プリンシパル
矢守 亜夕美
関連サービス