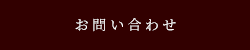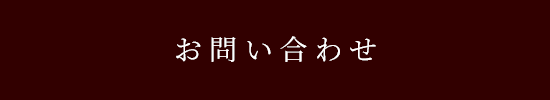近年、人権問題がビジネスにおいて極めて大きなインパクトを与えるものであることが認識されはじめています。一方で、ビジネスが具体的なアクションを起こすには、定量的に「数字で」課題の重要性を示していく必要があります。本シリーズでは「人権と数字」と題し、ビジネスにもたらすインパクトの大きさを明らかにします。第1回は人権ビジネスを数字で紐解きます。

※現代ビジネス「シリーズ『人権と数字』」2017年10月号の内容を一部変更して掲載しています。
I. 日本企業はいまだ「人権リスク」に鈍感
「人権」という言葉から、みなさんは何をイメージするでしょうか。「途上国における子どもの人身売買」「紛争地域における少数民族の迫害」などのように、日本人にとっては日常生活とは離れたところにある問題を頭に浮かべがちかもしれません。
しかし、人権問題とは、私たちにとって、もっと身近なものなのです。報道などでも頻繁に目にすることのあるセクハラやパワハラは言われなく人の尊厳を傷つける行為です。長時間労働や待遇の差別のような労務トラブルも不当に人を拘束したり、貶めたりする行為として立派な人権問題のひとつです。もし、自社のオフィスに障がい者が通行しづらい段差や物理的に入りづらい場所があるのならば、それも権利を侵害していると見なされる可能性があります。
世界は今、この人権問題に対する企業としての取り組みを求めています。2015年、ニューヨークにある国連本部において193ヵ国の首脳が一堂に会し「持続可能な開発のための2030アジェンダ」を採択しました。従来、発展途上の国々における問題解決に取り組んできた国連が、このアジェンダで掲げたのは「誰一人取り残さない」ことです。
もちろん、貧しい国々の子どもたちを守ることが役目です。しかし、それだけではない、もっと身近にあらゆる全ての国々において問題解決をすることが掲げられたのです。そして、そこで掲げられる17の目標とそれに付随した169のターゲットの中には、多くの人権問題の解決に関わる内容が記されています。
II. 誰もが賛成、のはずなのに
さて、人権問題の解決には誰もが総論で賛成です。それでありながら企業における人権問題について政府や消費者、そして企業自身の取り組みが十分でない理由のひとつは、人権問題のビジネスへのインパクトがリアリティある形で理解されていないからでしょう。
しかし近年、不幸な事件をきっかけとしながら、人権問題がビジネスにおいて極めて大きなインパクトを与えるものであることが認識されはじめてきました。違法残業労働で書類送検された大手広告代理店の株価は下落し、公的機関が同社の入札資格を停止しました。例えば厚生労働省は6ヵ月、ほかにも経済産業省や東京都、日本中央競馬会(JRA)はそれぞれ1ヵ月の入札停止を同社に言い渡しています。民間企業の中にも同様の判断をしたケースが存在するでしょう。
人権問題は「従業員や労組との小競り合い」のような軽い問題ではなく、経営者や株主にも直結する大きなビジネスインパクトあるものだという認識が出てきました。企業の課題解決を担う、大手の経営コンサルティングファームも企業における人権問題を取り扱う事例が増えてきています。企業の業績改善と人権問題の予防・解決が切り離せないものであることが、少しずつ理解されはじめてきたことの表れでしょう。
コンサルティングファームが企業の課題解決に携わる多くのケースにおいては、課題の重要性を経営者に対して「数字で」伝えることが第一歩となります。
人権の課題においても同様で、数字でインパクトを示すことが必要です。数字にしにくい印象がある人権に関しても公的機関の統計などから様々な数字が入手できます。例えば人権侵害を受けている人の数や人権侵害をなくすために取り組む主体の数など、国連を中心とした機関がデータを公開しています。
特に、今後関心がもたれるべきは、ビジネスに関する人権の数字になってきます。SDGsは政府だけではなく企業を主要な実施主体のひとつとして位置付けており、今後ビジネスにおいて人権課題への取り組みが強く要求されることは論をまちません。
本レポートでは、まず「人権ビジネス」に関わる数字を挙げます。環境ビジネスなどと比べると人権ビジネスについてはそもそもそれがどのようなものであるかが明確でなく、関連する数字もあまり把握されていません。
人権ビジネスの市場をどのように捉えることができるかを整理し、今後人権についても環境と同じように様々な法・規制、調達基準が形成されることにより、その市場が無視できないものに発展していくであろうということを見ていきます。
III. 「人権ビジネス」とはなにか
そもそも企業にとって「数字で見えないもの」を意識して事業活動を行うことは困難です。かつて「環境」はその典型的な例でした。例えば環境汚染により生じるコストがどの程度にのぼるのか、もしくは環境に配慮した製品がどの程度のビジネスチャンスとなるかがわからなければ、企業が注力するインセンティブは生じません。
今日、「環境」については様々なイシューが数字として把握されています。例えば「環境ビジネス」については各国において数十兆円の市場規模があることが示されています。日本の環境産業の国内外での売上をもとにした環境省の試算によると、2014年の環境ビジネスの市場規模は約105兆円程度とされます。他方で、「人権ビジネス」については、その定義が明確でなく数字としてあまり把握されていない段階にあります。人権ビジネスにはどのようなものがあるでしょうか。
まず、「人権問題」そのものに関わるビジネスとして、人権侵害やそれに対する取り組み状況を調査・評価するための人権デューデリジェンスや人権関連認証サービスが挙げられます。人権に関する意識啓発をはかるための人権教育教材・研修サービスも人権ビジネスのひとつでしょう。
このほかにも、人権侵害がそもそも起きないような生産活動ができるようにするための製品、例えば全ての人にとって働きやすい環境を整備するためのバリアフリー設備や、人間にとって危険・有害な労働などを人間のかわりに行ってくれるロボットも人権ビジネスの一部です。
さらに、企業の従業員のメンタルヘルス上の課題などに対応するEAP(Employee Assistance Program)や、人権侵害が発生した場合の法的サービス、被害者のケアを行うカウンセリングなどの医療的サービスも挙げられます。
さらに、企業の従業員のメンタルヘルス上の課題などに対応するEAP(Employee Assistance Program)や、人権侵害が発生した場合の法的サービス、被害者のケアを行うカウンセリングなどの医療的サービスも挙げられます。
IV. 人権ビジネスの市場は拡大する
環境について既に数十兆円~数百兆円規模の市場が確立していることのひとつの背景として、ビジネスに影響を与えるルールが早い段階から策定されてきたことが考えられます。
そもそも日本で「環境経営」という言葉が用いられるようになったのは1997年の京都議定書の前後からです。京都議定書を機に企業は事業活動の中に環境の視点を組み込み、環境報告書で自社の取り組みを公表するようになりました。
さらにポスト京都議定書と言われる2015年のパリ協定の交渉過程においては、“We mean business”(「我々はビジネスだ」/「我々は真剣である」の両方の意味を掛け合わせた企業・機関投資家グループ)に象徴されるように、むしろ企業自らが革新的な取り組みを行うことにコミットする形でルールの形成に大きな影響を与え、それが更なる市場の拡大につながっていったと考えられます。
一方、人権については比較的最近までビジネスに影響を与えるルールが策定されてきませんでした。「企業の人権尊重」を初めて明記した「ビジネスと人権に関する指導原則」が策定されたのは2011年のことであり、人権ビジネスの市場はようやく立ち上がろうとしている段階にあります。
ここ数年で各国における人権に関するルールの策定が急速に進んでいることに留意しなければなりません。米国では2012年に紛争鉱物規制ドッド・フランク法やカリフォルニア州サプライチェーン透明法が、英国では2015年に英国現代奴隷法が制定されています。
また、日本でもビジネスと人権に関する指導原則に従った国内行動計画(NAP:National Action Plan)策定が進められるほか、2020年には東京オリンピック・パラリンピック開催を見据えており、人権をはじめ持続可能性に配慮した調達などを世界に先駆けて実現することが求められています。こうした中で、人権ビジネスについても、環境の後を追う形で市場が拡大していくことが予想されます。
企業は美徳や倫理だけでは動けません。しかし経済合理性が認識できた場合、特に損益計算書での営業利益より上に表示される項目に影響があると把握されたとき、その対応力は急速に高まります。ビジネスにおいて人権対応を加速させるためには、数字で経営陣に示すことが何よりもパワフルなメッセージとなるでしょう。
CSR(企業の社会的責任)コストの範囲で漫然と対応するのではなく、自社ビジネスの業績向上のために社会課題解決に向き合う企業が増えたとき、世の中は加速度的に良くなると確信しています。
株式会社オウルズコンサルティンググループ
代表取締役CEO
羽生田 慶介
羽生田 慶介
マネジャー
石井 麻梨
石井 麻梨
関連サービス